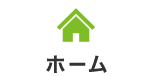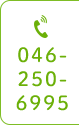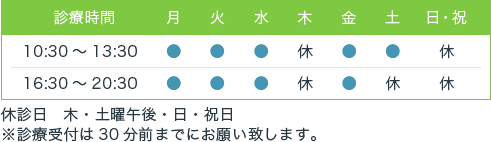日本精神科産業医協会
日本精神科産業医協会は、職場での産業医としての精神科医師や、精神科の知識を持った産業医のニーズが今後高まるとして、平成26年12月1日に設立されました。
精神科産業医としての技量や経験のある精神科医師のリストの公表や、会員企業に対して、精神科産業医の紹介やメンタルヘルス研修などのメンタルヘルス体制づくりの支援などを行なっております。
平成27年12月から労働安全衛生法改正で従業員が50人以上の事業場はメンタルヘルスチェックテストを義務化することとなりました。
高ストレス者は産業医面談を実施し診断治療の必要性があれば産業メンタルヘルスに精通した精神科医療機関への受診を勧めなければなりません。
ストレスチェックの実施は、その企業や職場の特徴を良く知っている産業医で、なおかつその産業医が精神科の知識を持っていることが望ましいとされます。